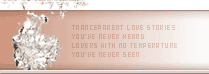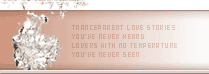asymmetrical panic
「あのさあバルト……、やっぱり、まずいんじゃないかな……」
水色のパジャマのボタンを器用に留めながら、フェイはなかばあきらめつつも、同居人に今日なんどめかの同意を求めた。
「なんで?べつに問題ねぇだろが」
対する同居人は、赤いパジャマを着込んで、すでにベッドにころがりながらそっけない返事をよこす。乾ききっていない金色の髪を盛大に散らして、せまいベッドに大の字になっているので、フェイはしかたなく共有領土のすみっこに腰を下ろした。
「そりゃ、問題ないって言えばそうなんだけど……」
いや、ほんとうに問題ないのか?とまたひとりでツッコミを入れて頭をかかえているフェイを、そろそろ睡魔となかよくなってきた同居人は、いつものことと捨て置くことにしたようだ。
なにが問題かといえば、発端は昨日の、ある人物との遭遇にある。
土曜日、授業を終えてバイトに向かうフェイは、5限が休講になったバルトと駅までのプチデートをたのしんでいた。
どうせすぐわかれなければならないとわかっている道のりだから、わざとゆっくり、相手を追い越さないようにあるく。
すぐにわかれたって、また夜にはいっしょにいるのだけれども。
それでも今いっしょにいられる時間はとてもたのしくて、夕食のメニューや休日の予定をああだこうだ言いながら、駅前のロータリーで信号待ちをしていると、ふいにバルトがとび上がった。
「シグ!」
そのまま、信号待ちももどかしげに走り出す、バルトの標的をあわててサーチすると。
大通りをはさんでも目立つ長身と、雑誌やドラマで見るような隙のないスーツ姿、黒光りする革靴に銀のスーツケース。のびきったTシャツにすり切れたジーンズの相方とはどうにもつりあわない、いわゆる「絵に描いたようなイイ男」が視界にとびこんできた。
反対側から横断してくる人の群れをかわしながらかけよると、くだんの「イヤみなくらいにイイ男」とバルトは、くるりと同時にフェイをふりかえる。
そんなに背がひくいわけではないフェイでもすこし見上げてしまうほどの長身と、チョコレイト色の肌、かるくウェイヴのかかった銀色の髪、人種の雑多なこの街でもそうは見かけない色彩だ。
でもいちばん目をひいたのは、相方とまったく同じ青の、でも格段に落ち着いたふたつの目だった。
目線でうながすと、バルトはとなりの「なんだか知らないけどとにかくイイ男」のうでをつかんで、フェイとの距離をつめる。
「あ、フェイ、こいつ俺のアニキ」
さらりと、こともなげに言い放たれたことばは、だから意外と言うよりやっぱり、というきもちを呼び起こしてもいいものだったのだが、それにしてもしばらくことばを失ってしまうほどには、衝撃的だった。
そういえばフェイと同居するまでは(というよりも一方的にころがりこまれたのだが)、バルトは兄弟で暮らしていたのだと、いつか聞いた。
しかし、そのとき想像した『バルトの兄像』と、目のまえの『真・バルトの兄』の距離は3万光年ほどもかけはなれていて、とっさのリアクションさえ出てこない。
「きみがフェイ君か」
しずかなパニックに追い打ちをかけるように、なじみのある青がまっすぐフェイを見た。
「シグルド・ハーコートだ。よろしく、フェイ君」
「あ、はい、ど、どうも……」
にこりと笑って手を差し出すしぐさは、とてもじゃないけどバルトと血縁関係にあるなんて信じられないほど隙のないもので、フェイはなぜかうろたえてしまう。
「きみのことはバルトから聞いてる。迷惑をかけてすまないな」
はい、と思わずうなずきそうになったフェイのあたまを、大迷惑張本人が力まかせにひきよせた。
「メーワクなんてかけてねぇよな、フェイ!」
「迷惑をかけている人ほどそういうものなんですよ、バルト」
「なんだとぅ!ひさしぶりに会ったってのに、失礼なヤツ!」
「真実をありのままに伝えると、礼は失われるものです」
微笑ましいような、しかしなにかズレてるような、兄弟の応酬が卓球よろしくくりひろげられている。
そう、あまりにナチュラルなのでつい聞き流してしまったが、なぜ弟に敬語で他人の俺にはタメ口なんだろう。
そんなフェイの素朴な疑問も、目の前のうるわしい兄弟愛にはあまり効果がなさそうである。
まったく会話にはいりこめず、兄と弟の間で視線をいったりきたりさせるフェイだったが、バルトのひとことでぴし、と固まった。
「じゃあさ、うちにあそびに来いよ!な?日曜だし休みだろ?よっしキマリな!」
「確かに休みですが……。お邪魔してかまわないのか?フェイ君」
おなじ青色の目が4つ、同時にフェイを見る。
それはフェイがとてもすきな色で、だから悪い魔女の魔法にかかったように、フェイはうっかり、承諾してしまったのだった。
しかしフェイは気がついたのだ。
この部屋に人を呼ぶ。
考えてみれば、バルトが居ついてから、いやフェイがこの部屋を借りてからはじめてのことだ。
いや、たしかにバルトの言うとおり、なにも問題はない、んだと思う。
……と、思うのだが。
男二人が暮らすのにベッドがひとつだって、べつに他人は気にしやしないだろう。
まさか、大の男がふたり、このせまいベッドにきゅうきゅうくっついて寝てるとは思うまい。
でも、イキオイで買ってしまった妙に横にながい枕(一般に新婚さん用という)はすこし、どうかと思う。
おそろいのマグカップとか、パジャマとか(だってバルトはやけにおそろいが好きなのだ) 、
そこらじゅうにころがってるものがぜんぶ、ふたつずつあるのもだいぶ、おかしいかもしれない。
そう、まるで。
これって、コイビトどうしの部屋みたいじゃないか?
いや、コイビトどうしだって、ここまでハズカシくないんじゃないだろうか。
そのへん、バルトはどう認識してるんだろうと思う。
そしてじぶんも。
自由にできる時間はできるかぎりいっしょにいて、べたべたとやたらくっついて、キスだってする。
そんな関係に、なんだかなしくずしに慣れてしまって、もうそれをおかしいとも思わないくらいなにかがマヒしてしまったけれど。
でも、じぶんたちがいわゆる『コイビトどうし』なのかと訊かれたら、バルトは、そしてじぶんも、迷わずノーと言うだろう。
おたがいのからだに、さわりたいと思うのはけっして、そういう理由ばかりじゃないのだ。
それでもすこし、他人をこの部屋に入れるのがハズカシいということは、そういう理由ばかりじゃないばかりではない、のかもしれない、じぶんにかぎっては。
いや、でも決定的にハズカシイことはしてないし。……まだ。
まだ?
まだということは、いずれはするつもりもなきにしもあらずということか俺!
「いや、そんなことは決して!」
つい叫んでしまったフェイに、バルトが不審げな顔をむける。
「おまえ、もしかしてつかれてンの?そーゆーときはさっさと寝るこった」
ほら、とスヌーピーのタオルケットをめくる先客に、フェイはなんだかいっきに疲れを感じた。
「そうだな……寝るか……」
げっそりしている同衾者に首をひねりつつも、バルトは手をのばして照明を落とす。ヒモにはしっかり、ぴかちゅう人形がぶらさがっている。
暗いオレンジ色の中で目を閉じようとして、フェイはふと思い出してバルトの髪をひっぱった。
「?なンだよ。寝るんじゃねぇの?」
「いや、あのさ、……シグルドさんって婿養子かなんか?」
フェイにしてはわけのわからない質問に、バルトは右目をすがめる。
「は?まだ結婚してねーよ、あいつ」
「だってほら、ラストネームがちがうだろ」
ああ、そゆことか、とバルトは笑って、ごろりと天井をむいた。
「ハハオヤがちがうんだ。さいしょはアニキだなんて知らなくてさ」
あ、とフェイは大きくまばたきをした。
そうか、それをさいしょに考えるべきだった。
でもそれは考えもしなかったんだ、
あんまりにもおなじ目をしてたから。
「ごめん、わるいこと訊いたか?」
「いんや、ぜんぜん。でさ、アイツうちにカテーキョーシに来てたんだよな。いっしょに暮らしはじめてからも、ずっとセンセイ口調でさ。アタマ、かてぇんだアイツ」
なつかしそうに目を細めるバルトは、なんだかとてもたのしそうで、フェイもつられて目尻をさげてしまう。
「なんで、家を出たんだ?」
仲よさそうじゃないか、と腕をつつくと、バルトはすこしきまりわるげにくちびるをゆがめた。
「だってよぉ、カッコわりィだろ、いつまでもこう……めんどうかけてばっかってのはさ。いっしょに暮らしてるとさ、どうしてもアニキ役もオヤジ役も、オフクロ役までさせちまうから」
それじゃあ今、俺にわがまま放題なのはなんなんだ、とは切り返さず、バルトらしいな、なんて思ってしまうじぶんに、フェイはやっぱりすこしハズカシくなる。
そういうのを一般に、『ごちそうさま』と言うのだが。
「でも、うらやましいな、あんな格好良くて頼りになりそうな兄さんがいて」
素直にそういうと、バルトはとろん、と表情をとかした。
そして得意そうにこんなことを言う。
「ダメだぜ、シグは俺のだからな」
「いや、べつに……」
横取りするつもりはないけど(ていうかなんかちょっと怖いし)、とまた正直にいおうとするが、
「皆まで言うな。おまえひとりっ子で、ずっと兄弟いなくてさみしかったンだろー?いやーおまえのあわれな少年時代がありありと目に浮かぶさ。かわいそうにな!でも安心しろ!今日からはこの、カッコよくて頼りになって、しかも時折ちょっぴりお茶目なオレさまのことを兄貴と思って慕うといいぞ!よかったな、フェイ!」
「……いないほうがまだマシ……」
いつものことながらこのマシンガントークの出所はどこなんだろう、となかばあっけにとられつつもついうっかり本音が口をついて出てしまった。
「ン?なんか言ったか?」
「い、いえ……なにも……」
さいわいにも上機嫌のバルトには、フェイの正真正銘本音は聞こえなかったらしい。
ハハハ、とかわいた笑いでごまかすと、バルトはにっこり笑ってフェイの首に手をまわした。
「そうか?ならいいんだ。 おやすみ、フェイ!」
そうして、いつものように、頬か目もとにかるいキス、……と思ったのだが。
「いでででででッッ」
「聞こえてンだよバカフェイ!」
思いっきり首の肉に歯を立てられて悲鳴をあげるフェイに、バルトはとどめとばかりに犬歯をくいこませる。
「だからって噛むなッ…痛いってバルト!」
やっとのことで狂犬をひきはがして、じんじんする首すじをおそるおそるなでると。
「ち、血が出て……。おまえどんな歯してんだもう!」
「こんな歯ー!」
いーっと、とがった犬歯を得意げにちらつかせて、それでもちょっと心配なのか、フェイの首すじに鼻先をつっこんでくる。
「……マジで血、出た?」
すこしちいさくなった声にほだされて、いやべつにたいしたアレじゃあ、なんてほんとはかなり痛いのに口ごもったフェイを、こんどはべつの意味で衝撃的な感触がおそう。
「うわっっっ、な、舐めるなーー!」
しびれる傷をぺろりと舐めあげられて、ほの暗い照明下でもあからさまに、赤くなったり青くなったりまた黒くなったりしているフェイに、バルトはひひ、と下品な笑いをもらす。
「これでよーし!じゃ、おやすみ!」
仕上げとばかりにちゅっ、と歯形の残るくびすじにくちびるをおしあてて、バルトはフェイの首にしがみついたまま、ことりとからだの力をぬいてしまった。
やっぱり今日もふりまわされっぱなしのフェイは、明日の来訪者にすこしばかりの不安をおぼえながらも、それでもまんざらでもなさそうにため息をついて、もう寝息をたてはじめたくちびるのはしに、かるくくちづけた。
もしかして俺は、ここにだれかほかの人間を、入れるのがいやなだけなのかもしれないと思いながら。
「……男所帯にしては、きれいにしているな」
娘の彼氏の部屋にお呼ばれした父親よろしく四方を見回したシグルドは、こうコメントしただけでフローリングに腰をおろした。
フェイ的にハズカシイ品々たちは、こっそりクローゼットに撤収済みである。
「クルマは?」
朝から上機嫌のバルトは、シグルドの横にぺたりとすわりこんでおみやげらしい包みをビリビリひきさいている。
「駅前のパーキングに置いてきました」
そのバルトから包みをとりあげ、器用に包装を剥くシグルドの、手つきにはなにやら年季が感じられる。
「なーんだ、ひっさしぶりにシグのクルマ、さわりたかったンだけどなぁ」
「さわってどうするんですか」
あなただって乗れるでしょうに、とシグルドが苦笑すると、俺はチャリでじゅーぶん、となぜか胸をはる。
なかよし兄弟にほのぼのしながらも、なんだかまだぎこちないじぶんを叱咤激励して、フェイはお茶の準備をはじめた。
そして。
午後、謎はすべて解けた。
シグルドがお客さま然として腰を下ろしていたのはほんのつかのま。
フェイが運んできた紅茶にすかさずミルクを落とし、バルトに手渡してやったのを封切りに、
弟がカップのなかみをこぼせばすかさず高価そうなハンカチでテーブルを拭いてやり、ケーキの中の洋梨(バルトはいつもほじくりだしてしまう)を抜いて皿にとりわけ、あげくのはてにはつめがのびすぎている、とバッグからマイ爪切りを取り出す始末。
世話焼き兄大作戦(しかも無意識の)を眼前にして、繰り出される匠の技の数々に、フェイは心の中で大きくうなだれた。
口ではきびしそうなことを言うけれど、はっきり言って、おそろしく甘やかしまくっている。
これが、誤爆型だだっ子製造マシンだったのか。
人前では分別ぶるくせに、いざふたりになると暴君まるだしになる、バルトのルーツをまざまざと見せつけられた気がした。
そんなことはあったが、シグルドは男のフェイから見てもすこぶる魅力的で、ふだんは皆無と言っていい落ち着いた会話なんかも楽しめたりして、いつもとはちがった意味で充実した休日になった。
3人でちいさなテーブルをかこんで、日もそろそろかげるころ、シグルドはすっと腰を上げた。
「それじゃあ、そろそろ私は……」
「え、もうかえンのか?まだいいだろ!」
がちゃん、とマグカップをテーブルでバウンドさせてバルトが抗議すると、シグルドはこぼれた液体をまたもふきとりながら、眉をしかめた。
「 ……バルト、ここはフェイ君のお宅だろう……。すこしは遠慮しなさい」
じゃあ、とスーツケースをカチリと閉めて、シグルドはさっさと玄関に向かう。
「フェイのうちは俺ンちだ!」
理由もなくえらそうなバルトに、シグルドは苦笑して、保護者の顔になる。
そして、バルトと 並んで見おくりの体勢にはいっている、フェイにすまなそうな笑みをむけた。
「すまないな、苦労してるだろう」
「はい、……あ、いえそんなことは」
思いきりバルトに足の小指をふまれて、あるがままのきもちを伝えられずにいるフェイのとなりで、バルトがなにか思いついたようにとびあがった。
「あ!シグ、ちょっと待ってろ!」
言いざま、くるりと方向転換してミニキッチンのある奥へひっこんでいく。
そしてなにやら棚を乱暴に開閉する音がして、フェイはああ、と思いあたる。
そんなバルトをふたりで見送って、ふっと視線が合うと、シグルドはやわらかく笑った。
思わずどきりとして、それでもフェイがぎこちなく笑いかえすと、シグルドはゆっくりと話しだした。
「あの子と一緒に暮らせるなんて、どんな子なんだろうと思っていたんだ。あの子は少し……事情も事情だし、普通ではないから」
「事情……?」
けげんな顔をするフェイに、シグルドはすこしおどろいたようにまぶたをうごかした。
「バルトから何も聞いてないのか?」
目線でうなずくと、シグルドはすこし考えて、またフェイに向きなおった。
「それなら、私からは何も言わないほうが良いだろう。私も、全部を知ってるわけじゃないんだ。……ただ、そうだな、軽い神経症みたいなものを持ってるから、気をつけてやってほしい」
神経症?バルトが?連想ゲームを24時間やったとしても、ぜったいに出てこない組み合わせに、フェイは混乱して、それでもなにかつめたいものが内臓に落ちこんだようなきもちになる。
うつむいてだまりこんでしまったフェイに、シグルドはいくらか姿勢をくずして話題を変えた。
「あの子は、いつも笑ってるだろう」
「え?あ、ああ……それはもうバカみたいに……あ、いえ、その」
「そう、だれかが見ている間はね」
ガシャン、と奥でなにかが崩れる音がして、会話はいったんとぎれた。
あちゃー、とかなんとか、ひとりで大騒ぎしている様子がばたばたと伝わってきて、ふたりは顔をあわせて苦笑する。
しかし、シグルドは口の端の笑みを消して、もういちどフェイの目をのぞきこむ。
「きみは見たことがないか?あの子が、人形みたいに表情を消して、何もないところをずっと見てるんだ。……私たちには見えないものを、時間を止めて、見てるみたいに」
そんなバルトは、見たことがなかった。
普通でない、といえばそれはどちらかというと躁気味なほどのテンションで、笑ったり怒ったり、感心するほど表情が変わる。
笑うことも怒ることも、泣くこともなかば忘れていたじぶんに、世界の色彩が塗りかえられるほどの感情を思い出させたのは、かれだというのに。
「でも正直、こんなに楽しそうなバルトを見るのは、ほんとうにはじめてのことだ。きみといっしょにいれば、そんなことも、もうないのかもしれない。あの子は、きみとここで暮らして、ほんとうにしあわせなんだろう。……だから、」
バルトとおなじ深い青色の目が、そこですうっとつめたい色に変わる。
「一度でも泣かせたら、きみを殺す」
ジョウダン、なんて言ったらそれこそ、その場で殺されそうなひくくてするどい声。
でも、そのときフェイの口をつぐませたのは、恐怖と言うよりむしろ。
のどもとまでせりあがってきたことばを吐き出そうとしたとき、がさがさとさわがしい気配が近づいて、フェイはまた声を喉奥にもどす。
見ると、パーティションに足をひっかけつつも玄関にたどりついたバルトが、ふたりのあいだにころがりこんできた。
にぱっと笑って、なにやら黒い物体が山と積まれた箱(クール宅急便の)をシグルドの顔につきだす。
「チョコクッキー!コレ、みやげに持ってけよ!甘いモン好きだろ、おまえ」
フェイといっしょにつくったんだぜ!と得意げにかかげる箱をがさがさとスーパーの袋に押しこみながら、なんだかすこし雰囲気のおかしいふたりに気づいて首をかしげる。
「どした?ふたりとも腹下したみてぇな顔して」
そういやシグ、腹弱ェもんなー、気ィつけろよ!とまるで見当違いに心配しているバルトを、シグルドはすこしまぶしげに見やって、甘そうなかたまりでいっぱいになった袋をうけとる。
「なんでもないですよ。……じゃあ、これはありがたくいただいていきますね」
そのままドアをあけようとするシグルドに、フェイがあわててつけたす。
「あ、それ……、チョコクッキーじゃなくて、ブラウニーですから!」
「どっちでもおんなじだろが!」
さっきまでのはりつめた空気は、その震源地ともいえるバルトの登場できれいにふきとんでしまい、フェイはこっそりため息をつく。
それは安堵かそれともべつのものなのか、フェイにもわからなかった。
「それじゃあ、バルト、……フェイ君も、また」
「また、来てください」
「じゃーなー!ゼッタイまた来いよ!!」
結局エレベータの前までついていって、まだぶんぶんと手を振るバルトにシグルドもフェイも苦笑する。
「なんかシグと話してたのか?」
外に面した通路から、まだシグルドを見送っていたバルトが、そう訊きながらくるりとふりむいた。
光をはね返して色を変える大きな青い目を見ながら、フェイは思う。
怒っても笑っても、泣いてもいないバルトなんて想像つかないな。
でもきっと、それは俺の知らない俺に見せない顔なんだろう。
だれにも。
さっき胃の中に入りこんだつめたいかたまりが、いっそう重さを増した気がして、でもめのまえに立つかれが、フェイのからだをこおりつかせてしまうそういったかたまりを、一瞬でとかしてしまうのもほんとうで。
「……いや、なんでもない」
「そーか?いやーでも今日はほんとに楽しかったな」
思いだすように目をほそめるバルトに、フェイもああ、とうなずいてみせる。
しかし、それにつづいたことばに、フェイは思わず足を止めた。
「ずっと、シグに会わせたかったんだ、おまえのこと」
ほんとうに満足げにわらう、 かれはきのうから、うたいだしそうに上機嫌で、その理由は。
なんだか、はずかしくも泣きそうになりながら、部屋にもどろう、とバルトの背を押して、なにげなくふりむいた一瞬に、フェイはシグルドのことばを思い出す。
俺は核弾頭よりもやっかいなものをいつのまにかしょいこんでしまったのかもしれないと、じぶんもじゅうぶんに危険度が高いことを棚に上げて考えて、……ふとこう思った。
シグルドは、あのスーパーの袋をぶら下げて駐車場まで歩いていくんだろうか、と。
** end **
|