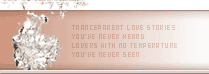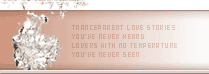daring, daring, daring?
3限で授業の終わる火曜日は、週末の次にバルトの好きな日だ。
教授が終業を告げれば、まっ白なルーズリーフをカバンにつっこんで講堂を飛びだす。
大学からは地下鉄で3駅の、商店街からすこしはずれた道に入る5階建てのマンション、休講だからと朝食もとらずに寝ていた相方が待つワンルーム。
今日はバイトも非番だと言っていたし、きっと今ごろはまだあのせまいシングルベッドで寝こけているだろう。
商店街で買いものをすませて、上機嫌で階段をかけのぼる。今夜のメニューと夜食がはいったスーパーの袋をふりまわさんばかりのスピードで。
「たっだいまー!」
バン!といきおいよくドアをけとばし、両手にかかえていた買い物袋をどさりと落として、玄関からさほど距離のないふたりの部屋に走りこむ。
上機嫌のタイムリミットが、すぐそこまでにじり寄っているのも知らずに。
「バルト様のおかえりだゼー!フェイーまーだ寝てんの……ぐぇッッ!?」
蛙がつぶされたらその時は声なんぞ出ないと思うのだが、そんなふうに形容するのがふさわしい奇声をあげて、バルトは文字どおり、固まった。
「なんだよ、おまえかよ……」
いっそなさけないほどがっかりして、そして3メートルほど後退する。
保身のための距離である。
「悪かったな」
そう言うわりにはまったく悪くなさそうな、むしろ楽しげともいえるうすら笑いをうかべて立っている、赤い髪の男。
イド、という名のその男こそは、バルトにとって目下のところの、天敵だった。
「厄日……」
何でこんな日にかぎって、なんて言ってもしかたない、肩を落として、玄関にほうった今夜の献立を取りに行くかと思いきや、
「あーーーーーッッ!!!」
ふたたび買い物袋をほうり投げて、仁王立ちしているイドに走り寄る。
警戒領域を踏み越えてしまったことには、さっぱり気づいていない。
「おいちょっとフェイ!ゼミの課題どーすんだよ!あしたの1限だっつの!出てこいおらァーー!」
バルトは自分のあたまにくっつくみつあみもゆれそうな勢いで、イドの赤いあたまを両手でつかみぶんぶんとゆさぶる。ゆさぶられているイドのほうは、ぴくりとも表情をうごかさない。
「……振って出てくるか。馬鹿が」
「あっおまえ今漢字で『馬鹿』っつったろ?もうあったまきた!今すぐフェイと交代しやがれこの完熟トマト!」
「うるさい……」
じゃれつく子猫をあしらうように、イドはバルトの両手首を片手でつかんで、彼にとっては軽くひねりあげる。しかし、バルトにとってはちっとも軽くはなく、見る間に顔から血の気がひく。
「いたいたいたいってぇーー!!折れるもげるとれるーー!!超いてえーーー!!」
あまりのさわがしさに、イドはフンと鼻を鳴らして獲物を解放したが、バルトは反動で壁にたたきつけられる。
力の加減がわからないというよりも、そもそも加減するつもりがないのだ。
なにしやがるバカヤロウ、とすぐさま反撃に出たいところだが、肺にうまく空気がはいらない。
なんとか呼吸をとりかえすと、すっかり感覚がなくなってふるえる手をさすりながら、バルトはようやくため息をついた。大学のゼミで知り合って、
さいしょはすこし、仲の良いともだち、そうして今ではかけがえのない、だいすきな同居人。
その彼が。
ときどき、記憶がとぎれるんだ、と、ほんとうにひくくて小さな声で、言った。
それは、いままで聞いたことのない、別人のような声だったので、バルトはそれだけで泣きそうになってしまった。
はじめは意識障害のようなものかと思っていた。
そのうち、自分の部屋で血まみれの猫や犬の死体が見つかるようになった。
とぎれた意識が戻るたびに、見覚えのない服のしみや泥に汚れた自分の足を見つけると叫びだしそうだった。
高校にあがるとすぐ家を出た。
だれと親しくなるのも怖かった。
でもずっと、だれかに助けてほしかった。
「あいつ」が俺の部屋にいたって聞いたとき、死のうかと思ったよ。
フェイがしずかにそう言ったそのときに、顔をぐしゃぐしゃにして泣いて、しがみついていったのは、バルトのほうだった。
ずっと悩んでいたことを、知らなかった。
出会ったばかりのころの、厚い壁をへだてて世界にひとりで立っているような、フェイを思いだしてじぶんが死にそうになった。
ふつうのともだちよりもたくさんの時間をわけあったって、ぜんぶをさらけだせるわけじゃない。
こんなに痛いと思ったって、フェイが痛かったことはぜんぶ消えない、じぶんは、フェイのことをなんにも知らない。
そんなあたりまえのことがわかって、バルトはほんとうにかなしかった。
フェイがずっとひとりでかかえこんでたものを、ぜんぶじぶんがうけとめられたらいいのにと、思った。
フェイは、それ以上話そうとしなかった。
でも、バルトにだって、フェイにでもおしえたくないことが、フェイだからおしえたくないことが、ある。
ずっと、死ぬまでひとりでかかえこんでいかなきゃいけないものだってあるのだ。
フェイだって、「あいつ」がバルトの前に現れることがなければ、きっとそうしただろう。
だからまだ、ぜんぶは聞けなかった。
ただとても、かなしかった。
「おい、金髪頭」
そんなバルトの切実な感傷を、いとも簡単に打ちやったのはイドのぞんざいな呼びかけだった。
「キンパツ頭じゃねえっての!俺にはちゃあんと、名前があるんだ立派ななまえが!」
イドはバルトを名前で呼ばない。
バルトだけではない、彼の口から人の名前が出ることはない。
ただ、フェイのことだけはきまって「あいつ」という。
フェイがイドをそう呼ぶように。
きっと、イドにとって、フェイ以外のすべてはどうでもいいものなんだろう、とバルトは思う。
ごく短い時間だけ世界に立ち、あとはフェイの中で半醒半睡の生を送るイドにとって。
そんなことを考えながら、バルトは最近、フェイだけでなくイドも、なんだかほうっておけなくなっているじぶんに気づく。
それはもちろん同一人物だから当然、なのだが顔も中身もまるで違うふたりを「おなじ人間」と認識できるような高等な情報処理能力をバルトは持ちわせていない。
フェイはどちらかといえば温厚で、かつ時にはバルトとはるくらいシンプルな情報処理系統を持っている。そのフェイのからだに、猛禽類並の攻撃欲と幼児並の嗜虐癖、出所のわからない蘊蓄とバルトには理解不能な思考パターンを持つイドという人格が同居しているのだ。
いったい何が起きているのか、バルトにはさっぱりわからない。
わからないことを考えるのはたいへん苦手なので、バルトは結局、なにも考えずにフェイはフェイ、イドはイド、とざっくり区別することにしてしまった。
そして、月に1度か2度のペースで現れるイドと接しているうちに、すこしだけ考えるようになった。
フェイの口からきいた「もうひとりのフェイ」 の姿と、バルトがつかのまいっしょに過ごすイドは、一致するようでどこかちがう気がするのだ。
たしかに、めちゃくちゃされるし、殺されかけたことも一度や二度ではないのだけれど。 と、バルトにしては深い思考に入りこもうとしていると、突然視界が大きくぶれた。
「……いて……いてえっつってんだろ!人の頭をなんだと思ってんだ!パーになったらどーすんだよッ」
「呼んでも答えないからネジが切れたのかと思ったんだ」
あらためてパーになる心配はないと思うぞ、とつけたして、イドは衝撃からまだ立ち直れず頭をかかえるバルトを目を細めて見やる。
どうやら、イドはこの調子でバルトをオモチャに時間をつぶす気らしい。
冗談じゃねえ、だいたいネジが切れたらしばく前に巻くモンだ、とバルトはまた3メートルの安全距離をとった。
「……なんだコレは」
約2時間後、イドは皿に盛られて湯気を立てているモノの素性を、表情には出ないものの不審げに問いただしていた。
「メシ!」
あれからたっぷりイドにもてあそばれたバルトだったが、なんとか気をとりなおして、夕食を完成させた。ほどけきってしまったみつあみをうしろでまとめて、赤いエプロンをひっかけた肩をそびやかせている。
「猫いらず入りか?」
「だーーッ!食いたくねえなら食うな!今日はな、フェイの好きなツナ入りオムライスにしようって朝から決めてたンだよ!決めてたのに作んねーとキモチワリィだろ!」
バルトはいいわけのようにわめきながらエプロンをはずして、イドとはなるべく距離をとってテーブルについた。
イドはその「オムライス」をめずらしげに見やりながら、スプーンで器用に検分している。
「オムライスというのはチキンライスを卵で包んだものだと思っていたんだが……。少し眠ってるあいだに調理法が変わったらしいな。どす黒いチャーハンを卵とじしたものを最近ではオムライスというのか。ありがたくいただくとしよう」
「もーおまえは食うな!食うんじゃねえ!」
まっ赤になって皿を取りあげようとするバルトをなんなくかわして、イドは黙々と食事をはじめる。そのイドを、しっぽを逆立てた猫のように威嚇しながら、バルトも自称オムライスをつつきはじめた。イドの攻撃を警戒しなければならないバルトは、食事中も気が気でなかったが、イドはきれいに食器のなかみをかたづけると、そのまま隣のベッドに陣取ってしまった。
ほっとしつつもなんだか拍子抜けして、横目でイドの様子をうかがうと、イドはそこはかとなく満足げな顔をしてベッドに長くなっている。
目を閉じてそのままうごかないイドに、ふと気がついてバルトがたずねた。
「アレ?今日はでかけねーの?」
いままで何度かイドが出てきた時には、いつのまにかいなくなっていて帰ってきた時にはフェイに戻っていたから、夜はなにか化け物の会合にでも出ているのかとバルトは思っていた。
「貴様がキャンキャンわめくから頭が痛い。……寝る」
「あっそ。おやす……」
そのまま食器のかたづけを、と思ってベッドに背をむけたバルトだったが、がしゃんと食器をシンクにほうりこむとイドにつめ寄る。
「み……ってちょっと待ったァ!おまえそこで寝るつもりかぁ!?」
「当然だ」
文句あるか、といわんばかりの顔でうすく目を開いたイドだったが、 ああ、と納得したようにかすかに眉をうごかした。
「貴様らはこの狭苦しいベッドで、わざわざ一緒に寝てるんだったな」
「なんだその言いかたはッ」
べつにやましいことなんかなんもしてないぞ、と耳まで赤くなって腕をふりまわしているバルトを、なにか思いついたようにイドはさえぎった。
「だったら、一緒に寝ればいいだろう」
「へッッ?」
「なにか問題があるか?やましいことがなにもないなら、普通に寝たらいいだろう、いつもどおりにな」
半分だけ開いた目は睨みつけているようにもみえるがくちもとは意地悪く笑っていて、バルトはからかわれていることに気づく。
イドの論旨は筋がとおっているようだが実はまったく意味のないもので、そんなものは無視すればよかったのだ。
が、もちまえの反骨心が災いした。
「ああ、寝てやろーじゃねえか、ぜんッぜん問題ねえな!」
買わなくても良い売り言葉を無意味に買ってしまったバルトは、このあと盛大に、後悔することになる。
「……なんにもすんなよ」
あとかたづけと風呂をすませて、 課題のレポートはさっぱりあきらめたバルトは、もうひとつなにかをあきらめて沈痛とも言える表情でベッドサイドに立っていた。
「貴様に対してベッドの中でするようなことをしてやる義理はないぞ」
「じゃなくて!夜中に馬乗りになって首締めたりとか……」
「……俺は地縛霊か」
イドはあきれたような声を出したが、バルトはかなり本気である。夜中に首だけ飛びまわったり、枕を裏返して悪夢を見せたりなんかはかるくやってのけそうなのだ。
おそるおそるといったふうにイドのとなりにもぐりこむバルトを、イドはなぜだか満足げにながめていたが、金色のあたまがすっかりタオルケットにおさまったのを確認して、ぼそりとこう言った。
「……まあ、あんまり動きまわるようなら、腕の一本くらいはへし折らせてもらうかもしれんが」
ガバッとおそるべき腹筋力を披露して、バルトはベッドからの脱出をはかる。
「や、やっぱ俺、床で寝るッッ」
「冗談だ」
あまり冗談でもない顔なのだが、つめたい手で肩をつかまれるとなんだかからだのちからが抜けるようで、バルトは取り憑かれたようにイドのとなりにおさまる。
フェイになったら、盛大にやつあたりをしてやろうと心に誓いながら。イドは、たしかになにもしなかった。
しかし。
バルトは眠りに対しては意外と神経質で、そういえば他人と寝るなんて、フェイと毎日のように同衾するようになるまでは考えられなかった。
おなじからだだと言っても、温度や呼吸はなんだかちがうような気がするし、背中あわせで眠るのには慣れていないのでなかなか寝つかれない。
からだは眠いのにいっこうに休まない頭をもてあましながら、バルトはいったいどうしてこんなことをしてるんだろうと、思う。
いますぐベッドを出て、床でぐっすり眠ればいいのだ。
でもなぜか、つめたい背中からはなれることができない。
ずっと、ともだちがほしかった。でも、「だれか」とともだちになりたいと思ったのは、フェイがはじめてだった。
はじめて、じぶんの手をにぎっていてほしいと思った。
手を、つかんでやりたいと思った。
でも、フェイのからだにはフェイがもうひとりいる。
だれの手もとらないで、ひとりで立っている、フェイの中のフェイでない男。
フェイを思うときのきもちとはまったくべつの、でもどこかよく似ている、きもちがのどもとにひっかかってないか?
まさか。
なかよくしたいと、思っているのだろうか?
こんな、笑って人を殺しそうな、人外魔境が服着て笑ってるような男と?
そんなバカな、冗談じゃねえ、ともだちどころか顔見知り……いや赤の他人だってごめんだぜ、とはんぶんわけのわからないことを思いながらちいさく身ぶるいすると、
「……うるさいぞ」
……思ったことがぜんぶ口に出ていたらしい。
なんとなく居心地がわるくなって、バルトはごそごそと身じろぎしながら、そっとうしろをうかがう。
「ぎゃっっ」
と、いつのまにかバルトのほうに向きなおって寝ていたイドと、はげしく至近距離で目が合ってしまった。
「なんでこっち向いてンだよッッ!」
今のは、ハンパじゃなく怖い。
葬式帰りの夜道で死に神と目が合ったのとおなじくらい、怖い。
ほとんど半泣きであとずさるバルトを、イドは心底たのしそうにながめている。
もしかして自分は、手のひらサイズの愛玩動物だと思われてるんじゃないだろうかと、またも泣きたくなりながらベッドぎりぎりまで後退するバルトだったが安物のシングルベッドはそんなに広くない。
気がつけばシーツを這っていた手は空をつかんで、あ、という間もなく、バルトは頭からフローリングにたたきつけられる、
と思ったのだが。「あ?」
ゴン、と床とご対面するはずのあたまはつめたい腕にささえられていて。
え、と思うまに、バルトはタオルケットの中にひきもどされた。
「静かに寝ろ」
いつのまにか起こしていた上半身を音もなくシーツにもどして、イドはくるりと背を向けてしまった。
なにがおこったのか理解できなかったが、とりあえずはバルトもイドに背を向けて今度こそ寝ようとする。
しかし、静かな時間は長くつづかなかった。
「おい!」
「静かに寝ろと言ってるだろう」
がばりとおきあがったバルトに、間髪いれずイドがつっこむ。
「ひょっとするとおまえ今、俺のこと助けなかった!?」
まぬけな沈黙が、こじんまりしたワンルームに落ちた。
きらきらと青い目をかがやかせて、世紀の発見をものにしたようなオーラを身にまとっているバルトを後目に、イドはふたたびごろりと寝にはいる。
「あっもしかして!」
「……うるさいぞ」
「おまえ照れてねぇ!?なあ!なあって!」
あまりの発見にすべての警戒心がとんでいってしまったのか、バルトはイドをゆりおこしにかかった。
「…………」
何も言わずおとなしくゆさぶられているイドには、いつものガイガーカウンタまで反応しそうな剣呑さはなく、バルトはまた、からだのどこかでひっかかっていたきもちがさわぎだしたのに気づく。
「なーイド、起きてんだろ?ちょっとここは、ひとつ腹をわって話してみようじゃねえか、男同士」
「…………」
「なー、なあって、イド、俺ずっと気になってたことがあんだよ」
「……なんだ……」
背中越しにぼそりと返事がかえってきたことに気をよくして、バルトはにんまりする。
そうして気がついてみれば、バルトはこの男にききたいことがたくさんあって、ききたいことがたくさんあることに、気づいたことがなんだか楽しくなった。
すこしずつ聞いていっても、いいんじゃないか?
あまりに予想外のできごとにナチュラルハイなあたまは、いつにもまして軽い。
たくさんのききたいことから、でもとりわけ、気になっていたこと。
「おまえのナマエさあ、だれがつけたんだ?」
「…………」
「あっもしかして自分でつけたとか?だっせェー!センスわりーなぁ、おまえ」
「………………」
ひゃははは、と涙目になって笑っていると、ふうっとからだが軽くなった。
と、思った次の瞬間、内臓を吐き出しそうな衝撃が全身を襲う。
白くなった視界がじわじわともどってきたとき、バルトはまったく自由をうしなった自分のありさまに気づいた。
背中は鉛のような重力にたわんでいて、首をよじって見上げると、ばさりと落ちかかった赤い髪からのぞく金色の目が、異様な光をはなってバルトを射すくめていた。
「よっぽど遊んで欲しいらしいな、バルトロメイ」
ひっ、と息をのんで、バルトはいまさら自分のお調子者っぷりを後悔するけれど、後悔はいつだって、ひとあしもふたあしもおそいのである。
氷みたいなてのひらがうなじを這って、いまにも力を込めそうなのに首をすくめても、ほんのすこしだって自由にならない。
バルトはぴくりとも動かない手足に念を送りながら、はかない抵抗でも今夜を生き延びるための算段に必死で、 はじめて、イドがじぶんのなまえを、ちゃんと呼んだことにはしばらく気づかなかった。
** end **
|